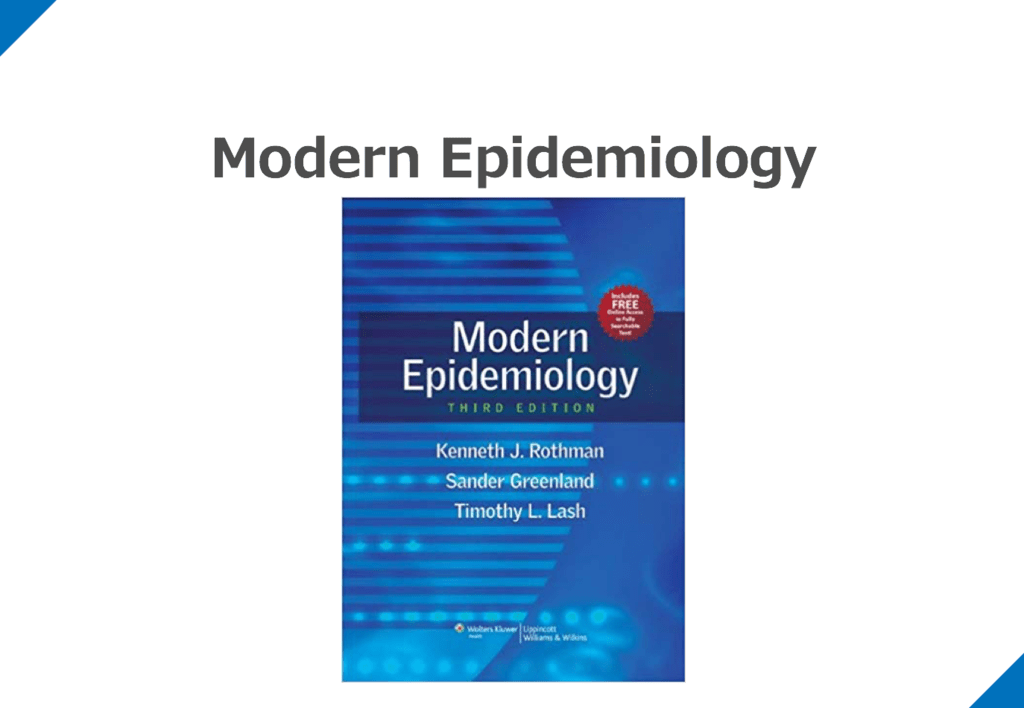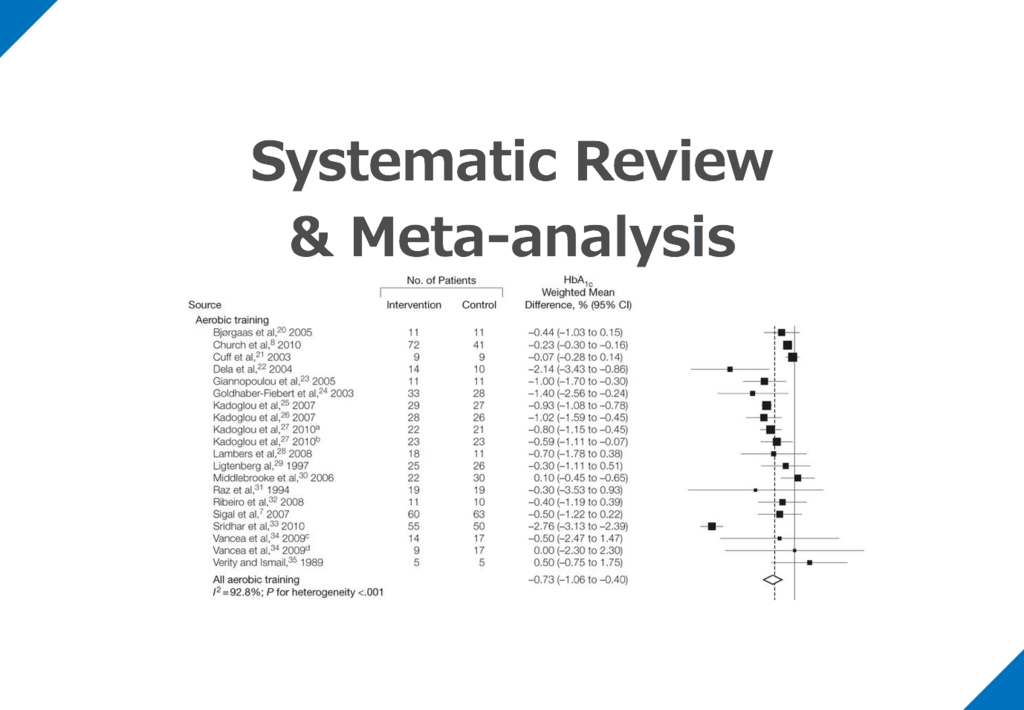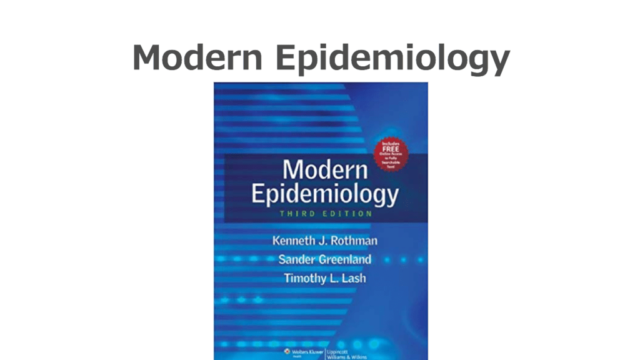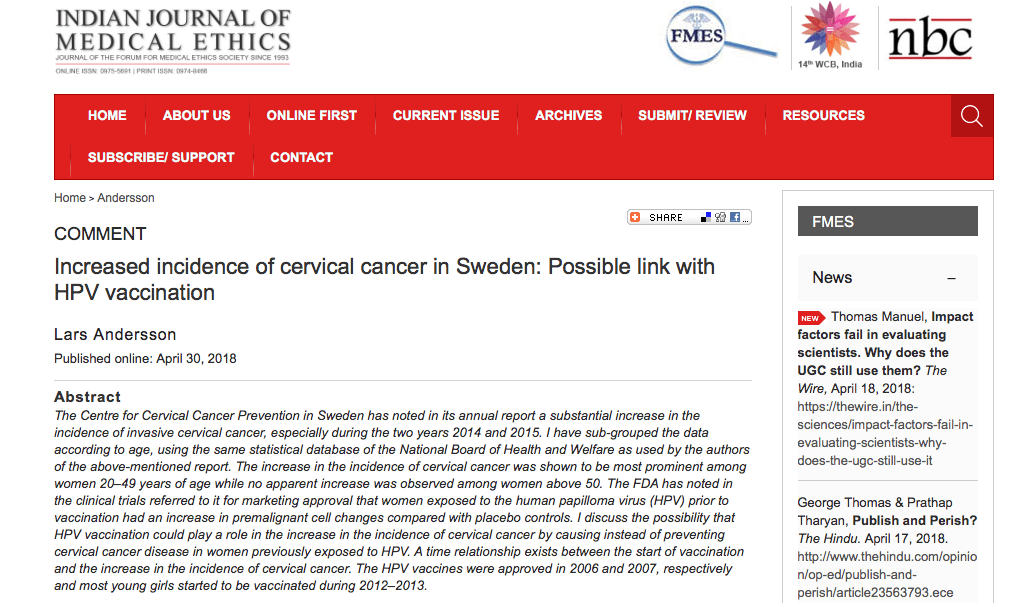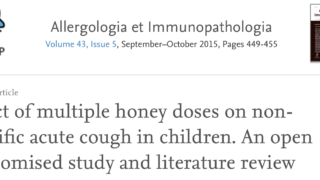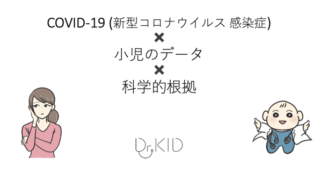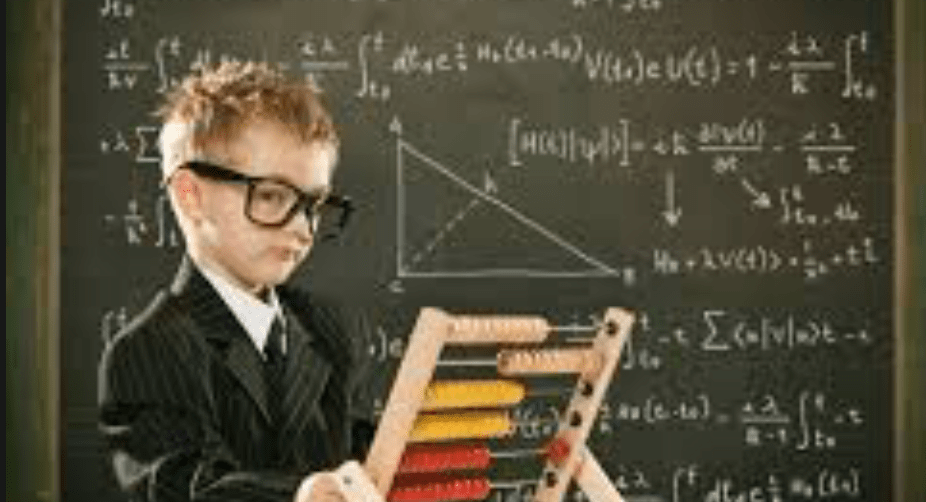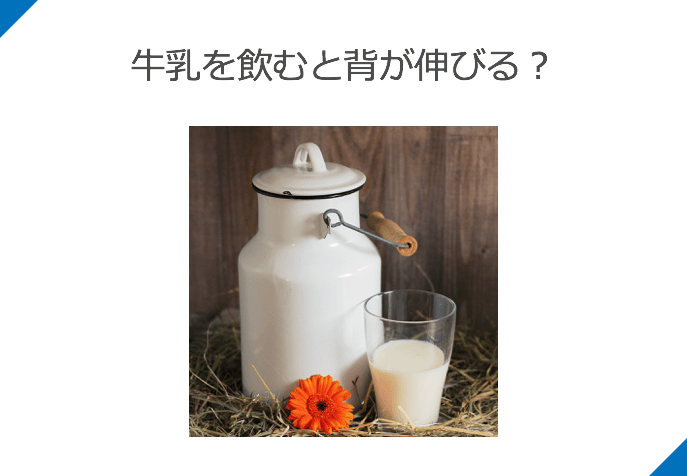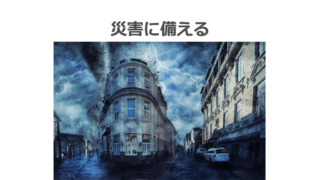前回はコホート研究の概要について解説してきました。
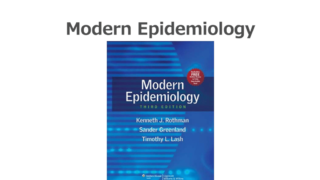
非常に完結に説明すると、コホート研究へ参加し、暴露を評価し、追跡し、アウトカムを評価し、コホートを終了させます。
前回説明しきれなかった点は多々ありますが、まずはコホートの入り口(最初)と出口(最後)について、少し詳しく説明していこうと思います。具体的には、
- コホートの入り口:対象集団の設定
- コホートの出口:打ち切り
の2点について、やや詳しく説明していこうと思います。
今回もModern Epidemiology(3rd edition)を基に記載していますが、直訳ではありませんし、私の解釈と背景知識を織り交ぜながらの解説になります。
今回も少しアレンジしていますので、ご容赦ください。
オープンな集団とクローズドな集団について
コホート研究では、参加者を募ったり、想定する母集団を決める必要があります。大負けに分けて、
- 対象集団がコホートに入る期間を固定する
- 対象集団がコホートに入る期間を固定しない
の2通りがあります。
対象集団を固定する場合(Fixed cohort/ Closed cohort)
追跡対象とする集団(コホート)に入る期間を固定する場合、「Fixed Cohort」といいます。
Fixed Cohortの場合、
- 定められた期間に患者を登録し(membership defining event)
- その後は新たに患者を追加しない
コホートを想定しています。
例えば、
- 1950年1月1日に広島・長崎に住んでいた人(原爆・被爆者コホート)
- 1994年〜1998年にドイツの人口登録票から年齢をもとに(女性, 35〜65歳;男性, 40〜65歳)、ランダムに参加者を抽出する(EPIC)
などがあげられます。
Fixed CohortとClosed Cohortについて
厳密な区別があるわけではなく、教科書によって記載内容も変わると思いますが、
- Fixed Cohort(固定したコホート)
- Closed Cohort(閉ざされたコホート)
という言葉を使い分けている疫学者もいます。
前者はこれまで説明した通り、参加者を募集する期間が固定されたコホートを「Fixed Cohort」と説明してきました。
コホートの場合、追跡不能(Loss to follow-up:LTFU)となる人が出てきてしまいますが、Fixed Cohortではこれの有無は問いません。
一方で、Closed Cohort(閉ざされたコホート)では、アウトカム以外で追跡不能となった人がいない状況を指します。より厳密なコホートと言えそうです。
(*実際のコホート研究で追跡不能が0になることはまずないです)
Fixed CohortやClosed Cohortの利点
利点としては、Cumulative Incidence (= Risk:例, 3 cases per 100 people over the 1 year period)やIncidence Rate (= Rate:3 cases per 100 person-months)を計算できる点にあります。
特に追跡不能の症例が少なければ、Riskを計算できます。仮に、追跡の症例が多くても、Rateは計測できます。
対象集団を固定しない場合(Open/ Dynamic Population)
一方、オープンコホートでは対象集団の出入りをある程度自由にします。
- 異なる期間でコホートに入ることができる
- 一度コホートから抜けても、戻ることが可能
など、ある程度の柔軟性が与えられた状態です。
オープンコホートは、別名でダイナミックコホートなどと呼ばれることもあります。
Open Cohortに利点
オープンコホートの場合、コホート研究が始まってからでも研究に参加できるため、サンプル数の確保がより楽になります。Fixed Cohortの場合、追跡不能の症例が多すぎると、コホート研究自体が台無しになり兼ねませんが、オープンコホートであれば、その心配は少なくなります。
一方で、解析はやや複雑になります。
まず、Riskを直接計算できなくなり、Rateを使用することになります。
さらに、コホートの出入りをする人は、それなりの理由(患者背景の違い)がありますので、コホートにずっといるメンバーと、途中で退出したり、入ってくる集団と比較可能か考慮する必要も出てきます。
コホートの出口と打ち切り(Censoring)について
コホートを終えるタイミングについてですが、
- 予め定めた期間に達した時
- 追跡不能となった時(つまりドロップアウト)
の2つが多いでしょう。
3つのCensoring(打ち切り)について
よく「censoring(打ち切り)」と説明されることがありますが、
- Left Censoring
- Interval Censoring
- Right Ceonsoring
の3つに分けられます。やや分かりづらい概念かもしれませんが、ここで簡単に説明しておきましょう。
まずは「Left Censoring」ですが、目的とするアウトカムが、研究が始まる前に既に発症している状態のことを言います。
次に、「Interval Censoring」ですが、アウトカムが一定の期間内でいつ生じたのか、はっきりと分からない状態を言います。
例えば2年毎に参加者のアウトカムを評価していたとします。2年前には血液検査でなかったアウトカムが、今回は認めた場合、どこで2年間のどの期間でアウトカムが生じたのか、分からない状態になります。この状態をInterval Censoringと言います。
3つ目の「 Right Censoring」は
- アウトカムが生じる前に追跡不能になった場合(Loss to follow-up)
- 研究が終了となり、追跡できなくなった(administrative censoring)
のことを指します。
まとめ
今回はコホート研究の入り口と出口について、簡単に説明してきました。
研究デザインによって行えるアウトカムの評価方法(Risk, Rate, Odds)が変わってきます。
また、入り口と出口を知ることで、よりコホート研究が短に感じられ、イメージしやすくなればと思います。
次回は、コホート研究における暴露因子(Exposure of Interest)の評価や、Immortal Person-Timeなどについて詳しく説明していきます。
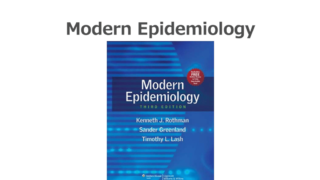
● Modern Epidemiology(3rd edition):Chapter 7: Cohort study